<本サイトは記事内にPRが含まれています>
オルカン(eMAXIS Slim 全世界株式オール・カントリー)は、世界中の株式に幅広く分散投資できる優れた投資信託として、多くの投資家に支持されています。
その中には新興国の株式も含まれていますが、構成比率は2024年時点で約10%と少なめです。
一見、全世界に投資しているようでいて、実際には米国の比率が非常に高く、米国市場の影響を大きく受けやすい点が見逃せません。
「オルカンだけで大丈夫なのか?」「他に何か組み合わせるべきなのか?」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
とくに、投資初心者の方にとっては、「オルカンを持っているけれど、それ以外に何を追加すればいいかわからない」という声もよく聞かれます。
本記事では、オルカンと新興国投資を組み合わせるべき理由や、その際に選ぶべきおすすめの投資信託、リスク管理のポイントまで詳しく解説していきます。
インドやベトナムのような高成長が期待できる新興国にどう投資すべきか、債券やバランスファンドとの組み合わせは有効なのか、といった疑問にも丁寧にお答えします。
この記事を最後まで読むことで、オルカンの特性を理解しつつ、自分に合った分散投資の戦略がきっと見えてくるはずです。
オルカンに新興国の組み合わせは必要なのか
オルカンは、全世界の株式に投資するファンドとして非常に人気があります。
中でも米国株の比率が高いことから、アメリカ経済の影響を強く受けやすいという特徴があります。
また、オルカンには新興国株式も含まれていますが、その割合はわずか約10%程度にとどまっています。
このため、新興国の成長性をしっかり取り込みたいと考えるなら、オルカンと別に新興国ファンドを組み合わせる選択肢が有効です。

新興国の成長を狙うなら、オルカンだけでは物足りない可能性がありますよ。
オルカンに新興国ファンドを加えることで得られるメリットは主に以下のとおりです。
- 新興国の高い経済成長を取り込める
- 地理的な分散効果が高まる
- 米国株偏重リスクを軽減できる
- リスク分散で暴落時の耐性が高まる
オルカンの構成比率は、時価総額に応じて機械的に決まります。
つまり、新興国の比率が自然に増えるには、その国の市場全体が成長して世界的に評価される必要があるのです。
これを待っていると、投資機会を逃してしまうこともあるでしょう。
そこで、新興国に特化したファンドを別で持つことで、自分のポートフォリオ全体のバランスを自分で調整できます。



オルカンに新興国入ってるなら、わざわざ別で買う必要ないってこともありますよね?



確かに入っていますが、全体の1割ほどしかなく、国ごとの偏りもあるため、自分で補うことで成長国の恩恵をより多く受けられます。



なるほど、例えばインドとかに投資したいなら別でインド株ファンドを持った方がいいってことですね!
新興国ファンドは、短期間で大きなリターンが狙える一方で、為替変動や政治的なリスクもあるため注意も必要です。
特に、経済成長が期待されている国ほど、規制や制度変更によって市場が不安定になることもあります。
このため、新興国ファンドを組み合わせる際は「成長性」と「リスク」の両面を見ておくことが大切です。
繰り返しますが、オルカンに新興国のファンドを組み合わせることで、全体の成長性と安定性をバランスよく持つことができます。



オルカンだけでは新興国の成長は十分に取り込めません。補完する投資でリターンとリスクを調整しましょう。
オルカンに新興国株式を組み合わせる理由
オルカンにはもともと新興国株式が含まれていますが、その比率は約10.3%程度にとどまっています(2024年4月30日時点)。
新興国の経済成長をしっかり取り込むには、この程度の比率では物足りないと感じる投資家も少なくありません。
そのため、別の新興国株式ファンドを追加して、自分で投資比率を調整する戦略が有効になります。



新興国ってすごく成長してるイメージありますけど、オルカンだけだと10%しか投資されてないんですね!



そうなんです。オルカンは時価総額に応じて自動で構成比率が決まるので、新興国比率は少なめなんです。
一方、個別の新興国株式ファンドには、成長性の高い国や地域に重点的に投資できるメリットがあります。
異なる投資先や運用スタイルを持つ商品を組み合わせることで、暴落リスクへの備えにもなります。
これは投資の基本である「分散投資」の考え方そのものです。
たとえば、オルカンと新興国株ファンドを組み合わせれば、米国偏重のリスクを軽減しつつ、アジアや中南米など成長性の高い地域の恩恵も得られるでしょう。
オルカンのデメリットは為替差損の発生
オルカンの投資対象のほとんどは海外株式です。
そのため、為替の影響を大きく受けるというデメリットがあります。
特に円高になった場合には、株価が上がっても為替差損によって資産が目減りすることもあります。
ここ数年、日本は1ドル100円台から150円台へと急激に円安が進行しました。
こうした為替変動に左右されない投資対象として、日本株や為替ヘッジなしの新興国ファンドが注目されているのです。



えっ、為替ってそんなに影響するんですか?株だけ見てればいいと思ってました!



為替も含めて資産価値に直結する要素です。とくにオルカンのように外国資産がメインの投資信託は、為替の影響を避けて通れませんよ。
新興国株式ファンドを取り入れることで、為替リスクの分散効果も得られる可能性があります。
さらに、日本株や新興国株を組み合わせることで、為替影響を抑えつつリターンを確保するという戦略が実現できます。
投資戦略
オルカンと新興国株式ファンドを組み合わせるには、戦略的な設計が重要です。
まず基本は「分散投資」。これは、リスクを抑えながら安定した成長を目指すうえで欠かせません。
- 複数国の新興国に分散して投資
- 異なる地域(アジア、中南米、アフリカなど)に分散
次に大切なのが「長期投資の視点」です。
- 短期的な価格変動に一喜一憂しない
- 成長ポテンシャルを最大限に活かす
新興国は短期的には不安定なこともありますが、長期的には経済成長が見込まれる有望な地域が多く存在します。
予想される成果
新興国株式ファンドを加えることで、期待できる成果は主に「高リターン」と「リスク管理の強化」です。
経済成長率の高い新興国に投資すれば、資産価値の上昇につながる可能性があります。
- 市場拡大による株価上昇
- 人口増加による消費拡大
さらに、複数国・地域への投資によって、特定国のリスクを軽減することができます。
- 政治や経済の安定を重視した国を選ぶ
- 為替やカントリーリスクを分散する
このように、オルカンに新興国株式ファンドを組み合わせることで、高い成長性を狙いながらも、全体のリスクを抑えたバランスの取れたポートフォリオが作れます。



新興国ファンドを加えることで、リスク分散と高リターンの両立が期待できます。未来の資産形成に大きく貢献してくれるでしょう。
オルカンにおすすめの新興国の組み合わせ
オルカンと新興国株式ファンドを組み合わせることで、より高い分散効果とリスク管理が可能になります。
特に、新興国市場は成長ポテンシャルが高く、地域によって経済状況も異なるため、異なる地域や運用スタイルのファンドを選ぶことがポイントです。
それぞれのファンドをうまく組み合わせることで、暴落リスクへの耐性を高めながら、成長の恩恵を受けるポートフォリオを構築することができます。



どの新興国ファンドを選べばいいのか迷っちゃいます…



選ぶポイントは「国の成長性」「運用スタイル」「分散効果」。それぞれのファンドの特徴を見ていきましょう。
以下に紹介する投資信託は、オルカンと相性が良く、組み合わせることで得られる効果も大きいものです。
- 新興国市場の成長性を取り込める
- 地域の分散効果を高める
- 異なる運用スタイルを加えることで収益源を多様化
- 米国株偏重のバランスを取る
それでは、まずは新興国インデックス型ファンドの代表例を見ていきましょう。
①新興国株式インデックスの投資信託(SBI・フラトンVPICファンド)
「SBI・フラトンVPICファンド」は、アジアを中心とした4つの新興国(ベトナム、パキスタン、インド、中国)の株式に分散投資するインデックス型のファンドです。
投資割合の目安はインドと中国がそれぞれ30%、ベトナムとパキスタンが20%ずつと、アジア圏に広く分散されています。
このファンドの最大の特徴は、経済成長が著しい国々へのバランスの取れた分散投資ができる点にあります。
また、低コストのインデックス運用でありながら、複数の高成長国をカバーしているため、長期投資に向いています。



インドも中国も入ってるんですね!それならバラバラに買わなくてもまとめて投資できるんだ!



そうです。複数の国に一括で分散できるのが、このファンドの強みですね。
このファンドを選ぶ理由・メリット
- アジアの成長国にバランスよく投資
- 新興国全体の景気拡大に連動したリターンが狙える
- インデックス型でコストが低め
- 地域分散が効いていて個別国リスクを抑えられる
デメリット・注意点
- 為替リスクが大きい(為替ヘッジなし)
- 信託報酬がやや高め(年率2.13%)
- パキスタンなどリスクが高めの国も含まれる
- ボラティリティが高く、短期では値動きが荒くなることも
特にパキスタンやベトナムといった国は、急激な経済変動や政治リスクがあるため、長期保有を前提とした投資が求められます。
また、信託報酬がやや高めなので、毎月分配型などと勘違いしないよう商品内容の確認はしっかり行いましょう。
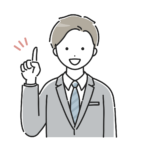
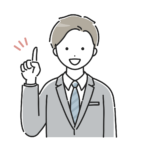
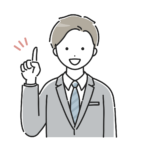
でも、ひとつのファンドで複数国に分散できるのは魅力ですね!初心者にも扱いやすそうです!



はい、まさにその通りです。はじめての新興国投資として、とてもバランスが取れたファンドです。
このように「SBI・フラトンVPICファンド」は、成長性の高いアジア新興国に広く投資したい方にとって、非常に有効な選択肢になります。



新興国の成長を一括で取り込めるこのファンドは、分散と成長を両立したい人にぴったりの選択です。
オルカンに組み合わせおすすめ新興国のファンド
②国内外の株式・債券・REIT(不動産投資信託)などに分散投資するバランスファンド
バランスファンドは、株式だけでなく債券やREITといった異なる資産クラスに投資することで、リスクを分散できる投資信託です。
オルカンは株式メインの構成なので、これにバランスファンドを加えることで、相場の下落に備える安定的な資産設計が可能になります。
②-1 eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス
このファンドは、国内外の株式・債券・REITに幅広く投資することで、1本でグローバルな分散投資ができる設計です。
eMAXISシリーズらしく、低コスト運用で長期保有に適しています。
- 株式・債券・REITに幅広く分散
- リスクを抑えた安定運用が可能
- オルカンとの相性が良く、補完しやすい
- 信託報酬が低く、コスト負担が軽い
一方で、REITや債券の比率が高くなることで、リターンがやや抑えられる傾向にあります。
- 成長性は限定的
- REIT市場の変動リスクも抱える



初心者の私でも、いろんな資産に投資できるって安心感があります!



まさにそうですね。守りを固めたいときの強い味方になりますよ。
特に値動きが激しい時期においては、こうしたバランスファンドがあると、ポートフォリオのブレが少なくなります。
②-2 りそなラップ型ファンド(成長型) 愛称:R246(成長型)
R246(成長型)は、プロの運用担当者が市場環境に合わせて柔軟に資産配分を調整するラップ型ファンドです。
成長型という名の通り、やや積極的な運用スタイルが特徴です。
- プロが自動的に配分を調整
- 市場の変化に対応しやすい
- 株式、債券、REITなど多様な資産に対応
- 個人では難しい調整をお任せできる
ただし、信託報酬が高めである点や、運用の透明性がやや分かりづらいという声もあります。
- コストがやや高め(1%以上)
- 運用内容の詳細が見えにくいことも



先生、これっておまかせできるってことですか?めちゃ楽そう!



そうですね。手間はかからないですが、コスト面はしっかり確認してくださいね。
オルカンで攻めつつ、このような成長型のバランスファンドを加えることで、メリハリのある運用が可能です。
③特定の地域やセクターに特化した新興国ファンド
オルカンが広く浅く投資しているのに対し、特定の地域や産業に集中投資するファンドを組み合わせることで、ピンポイントにリターンを狙うことができます。
高成長が期待されるテクノロジーや、中国のような大型新興国を補完できるのがポイントです。
③-1 フィデリティ・テクノロジー・イノベーション・ファンド
このファンドは、世界のテクノロジー企業に重点的に投資するアクティブ型ファンドです。
新興国の成長市場であるIT・AI分野にも積極的に投資しているのが特徴です。
- AI、クラウド、ロボティクスなどに注目
- 成長企業への集中投資
- インドや中国などの新興国企業も多く含む
その反面、値動きが激しく、短期的には価格が大きく上下するリスクがあります。
- ボラティリティが高い
- 運用コストが高め



テクノロジーって成長すごそうだけど、値動きも激しそうでちょっと怖いです…



そうですね。だからこそ、オルカンのような安定型と一緒に持つとバランスが取れるんです。
③-2 中国特化型ファンド(eMAXIS Neo 中国株式)
このファンドは中国企業の中でも、未来型産業に投資するインデックスファンドです。
新エネルギーやIT、自動運転など、将来性の高い分野に重点を置いています。
- 中国の次世代成長企業に集中
- テーマ型で時流に乗った投資
- オルカンで薄い中国比率を補える
ただし、中国経済や政治リスク、規制の影響など、不確定要素も多いため、慎重な判断が必要です。
- 政策変更リスクが大きい
- 一部企業の透明性に不安あり



先生、中国って規制とか厳しいってニュースで見たことあります!



はい、その分リターンも期待できますが、分散と比率調整はしっかりしましょう。
このような地域特化・セクター特化型ファンドは、オルカンの「広く浅く」投資とは対照的な存在です。
リスクは高くなりますが、投資に厚みとアクセントを加えたい方には魅力的な選択肢です。



特定の地域やテーマに特化したファンドは、成長性を狙いたい人の強力な武器になります。
③eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
「eMAXIS Slim 新興国株式インデックス」は、三菱UFJ国際投信が運用する低コスト型のインデックスファンドです。
MSCIエマージング・マーケット・インデックスに連動するパフォーマンスを目指しており、新興国全体に広く分散投資できます。
アジア、南米、東欧、中東など20カ国以上の新興国に投資しており、地域の偏りが少ないのが魅力です。
- 低コストで新興国全体に分散投資
- 信託報酬が年率0.19%(税込)と安い
- MSCIエマージング指数に連動
- ベーシックで扱いやすいファンド
特に、新興国投資をはじめたい方にとっては、コスト面・商品性ともにバランスが良く、導入しやすいファンドです。
一方で、以下のようなリスクもあるため、理解した上で組み合わせを検討しましょう。
- 新興国通貨の為替変動リスク
- 地政学リスク(政変・戦争など)
- 短期では値動きが非常に激しい



先生、これは新興国全体に投資できるってことで安心感ありますね!



そうですね。まずはこのファンド1本からスタートするのもおすすめですよ。
「eMAXIS Slim 新興国株式インデックス」は、安定した新興国分散投資を目指す投資家にとって、非常に有効な選択肢です。
オルカンとの組み合わせでは、オルカンの米国偏重部分を補いながら、新興国の成長にもアクセスできます。



低コストで新興国全体に投資できるこのファンドは、オルカンの弱点を自然に補ってくれます。
④8資産均等型ファンドの組み合わせ
8資産均等型ファンドは、日本・先進国・新興国の株式と債券、さらにREIT(不動産投資信託)を合わせた8つの資産クラスに均等配分するバランス型ファンドです。
代表的な商品としては、「eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)」があり、信託報酬も0.143%以内(税込)と非常に低コストで人気を集めています。
- 株式・債券・REITの全資産に均等投資
- 1本でグローバル分散が可能
- 信託報酬が低くて長期投資向け
- 積立NISA対応で利用しやすい
特に、オルカンのように株式に偏ったポートフォリオと組み合わせることで、バランスを整え、下落相場でも比較的安定した運用が可能になります。
- 株式の暴落時に債券・REITでカバー
- 経済変動に強い構造
ただし、均等型であるがゆえに、成長市場への集中投資はできず、爆発的なリターンは期待しにくい側面もあります。
- 成長性はやや物足りない
- 配分比率が固定のため柔軟性に欠ける



私みたいな初心者でも安心して持てるファンドって感じですね!



はい、守りを強くしながらも、世界中に資産を分散できるのがこのファンドの魅力です。
「eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)」は、オルカンとの補完関係を意識した長期資産形成にぴったりです。



8つの資産に分散されたこのファンドは、オルカンと組み合わせることでバランスの取れた投資が実現します。
オルカンと新興国投資の具体的な組み合わせのポイント
オルカンを軸にした投資は、世界の株式市場に広く投資できる優れた手段です。
しかし、オルカンは米国株に偏った構成になっており、新興国の比率は約10%程度と低めです。
そのため、新興国の高成長を取り込むには、別のファンドを組み合わせてバランスを整えることが重要です。
ここでは、具体的にどのように組み合わせればよいか、リスク許容度別に解説します。



先生、自分に合った組み合わせって、どうやって決めればいいんですか?



まずは「自分がどれだけリスクを取れるか」を知ることから始めましょう。そこが基準になります。
リスク許容度に応じて、以下のような戦略を立てていくと良いでしょう。
- リスク許容度が低い:債券・バランス型中心(オルカン90%、新興国10%)
- リスク許容度が中程度:株式を中心とした構成(オルカン80%、新興国20%)
- リスク許容度が高い:成長資産を多めに(オルカン70%、新興国30%以上)
- どのレベルでもリスクヘッジを意識する
ポートフォリオにおけるオルカンと新興国株式の比率の考え方(例:80:20、70:30)
ポートフォリオ設計では、オルカンを「コア」、新興国株式ファンドを「サテライト」として構成するのが一般的です。
この考え方は、安定した運用と成長性のバランスを保つのに役立ちます。
- コア:オルカンで世界市場全体に投資(70~90%)
- サテライト:新興国や特定セクターで成長狙い(10~30%)
オルカンが安定を支え、新興国ファンドが収益の「伸びしろ」を担う構成です。
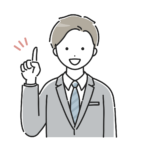
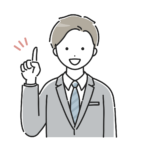
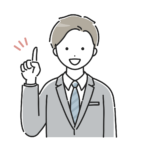
70:30とかの比率って、目安にするとすごくわかりやすいですね!



そうですね。まずは無理のない範囲で、新興国ファンドの比率を決めるとよいですよ。
オルカンに不足する新興国へのエクスポージャーを補完する
オルカンの新興国比率は、時価総額ベースで機械的に決まっているため、自分で比率を調整することができません。
このため、新興国のエクスポージャー(投資比率)を自分で高めたい場合は、個別に新興国ファンドを加えるのが最も効果的です。
- eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
- SBI・フラトンVPICファンド
- 地域特化型(中国、インド、ベトナムなど)
こうしたファンドを追加することで、ポートフォリオ全体に占める新興国の比率を20~30%程度まで引き上げることが可能です。
より高いリターンを追求する戦略
新興国ファンドを組み合わせるもう一つの理由は、「高いリターンを狙うこと」です。
新興国は人口増加、経済成長、インフラ整備などによって、中長期で大きく成長する余地があります。
- インドのIT産業
- 中国の新エネルギー分野
- ベトナムの製造業拠点化
これらの国や分野に投資することで、オルカン単体では得られないリターンを期待できます。



先生、でもリターンが高いってことはリスクも高いってことですよね?



おっしゃる通りです。だからこそ、比率は慎重に決めて分散を意識することが重要です。
分散投資効果の最大化を狙う
新興国ファンドを加えることで、経済圏・通貨・セクターの分散が可能になります。
それにより、ひとつの市場の下落に左右されにくくなり、リスクを抑えたポートフォリオが構築できます。
- 米国依存を避ける
- 新興国と先進国の経済周期の違いを活用
- 異なる通貨によるリスク分散
長期的には、これらの工夫がリスクを抑えながら安定したリターンを生む鍵になります。



オルカンと新興国ファンドを組み合わせれば、バランスよくリスクを抑えつつ、成長も狙えますよ。
新興国投資がポートフォリオにもたらす効果(分散投資、リターン向上)
新興国投資をポートフォリオに加える最大の利点は、分散効果と成長性のバランスを高められる点です。
オルカンのような全世界型ファンドでは、新興国の比率が10%前後に抑えられており、新興国の成長を十分に取り込むにはやや物足りない構成です。
そこで、新興国特化型ファンドを組み合わせることで、以下のような効果を期待できます。
- 異なる経済サイクルへの分散
- 通貨リスクの分散
- 高成長による資産拡大の可能性
- 先進国市場との相関性の低さ
このように、新興国への投資は、先進国だけでは得られない成長機会と分散効果をもたらしてくれます。



先生、新興国って値動きが激しいけど、やっぱり入れた方がいいんですね!



激しいけれど、その分リターンも大きいです。だからこそ、比率と組み合わせが重要なんですよ。
投資期間や目的に応じた商品選択のポイント
新興国投資に限らず、商品を選ぶときには「期間」と「目的」に合わせてファンドを選ぶことが成功のカギになります。
短期的なリターンを狙うならアクティブ型、長期で安定した成長を期待するならインデックス型が向いています。
- 長期投資:インデックス型(低コスト・分散性)
- 中期投資:地域・テーマ型ファンド
- 短期投資:アクティブ型ファンド(値動き重視)
例えば、20年以上の資産形成を目指すなら、eMAXIS Slim 新興国株式インデックスのような長期保有向けファンドが最適です。
一方で、直近数年で結果を出したい場合は、テクノロジーや特定国に特化したアクティブ型を選ぶと良いでしょう。



投資目的に合わせて商品を変えるって、すごく大事なんですね!



はい、目的と期間がはっきりすると、どのファンドを選べばいいか自然と見えてきますよ。
新興国選定のポイント
新興国といっても、国によって成長性・安定性・投資環境はまったく異なります。
ここでは、新興国ファンドを選ぶ際に見るべきポイントを紹介します。
- 経済成長率:高成長国はリターンが大きい
- 政治の安定性:政情不安定だと投資リスクが高まる
- インフラの発展:整備状況により企業成長力が左右される
経済成長が見込めても、政治が不安定な国では、せっかくの投資が台無しになるリスクもあるため注意が必要です。
また、交通網や電力、通信といったインフラの整備状況も、企業活動や市場発展に大きく影響します。



インフラって、企業だけじゃなく投資にも関係あるんですね!



もちろんです。投資先の国の基盤が整っていないと、どんなに成長していても企業が伸びませんからね。
おすすめの新興国
現在注目されている新興国の中でも、特に投資家から人気があるのが「インド」「ベトナム」「ブラジル」です。
インド
インドは世界で最も人口が多く、若年層の労働力が豊富です。
IT産業をはじめ、製薬や製造業でも国際競争力が高く、政治の安定性も評価されています。
- 高い経済成長率
- 人口ボーナスと消費拡大
- 安定した民主主義体制
- インフラ投資も急ピッチで進行中
ベトナム
ベトナムは近年、製造業の拠点として急成長しており、多くの外資系企業が進出しています。
若い労働力と政府の経済開放政策によって、今後も安定した成長が期待されます。
- 急速な経済発展
- 外資を誘致する政策
- 若年人口の多さ
ブラジル
ブラジルは豊富な天然資源と広大な国内市場を持つ南米の大国です。
資源価格の上昇時には、資源輸出国として経済成長が加速します。
- 広大な農地と豊富な資源
- 中南米最大の消費市場
- 政治・経済の安定化が進行中
このように、国ごとの特徴を理解したうえで、自分の投資スタイルに合った国・ファンドを選ぶことが、新興国投資成功のポイントです。



成長性だけでなく、政治やインフラもチェックして、投資先を見極めましょう。
新興国投資における注意点
新興国投資は高い成長ポテンシャルが魅力ですが、その反面、特有のリスクも多く存在します。
ここでは、新興国に投資する際に気をつけておくべきポイントを具体的に解説していきます。



先生、新興国って成長は魅力だけど、ちょっと怖いイメージもあります…



正しい知識があれば、リスクは管理できますよ。一緒に確認していきましょう。
新興国投資の魅力とリスクも考える
新興国は人口増加、消費拡大、インフラ整備など成長の原動力が豊富で、投資先として大きな可能性を持っています。
ただし、先進国と比べて政治・経済の不安定さ、為替変動の影響を強く受けやすいのが現実です。
具体的な例を挙げて見ていきましょう。
新興国市場の高い経済成長率
インドやベトナムのような新興国は、年間5~7%の経済成長を続けています。
これにより、株式市場も中長期では上昇が期待され、投資によるリターンも高くなります。
- インド:人口増加とIT産業が強み
- 中国:新エネルギー・製造業が成長
- ベトナム:外資誘致と若年層が活力
こうした国々では、国内消費の拡大と輸出の強化により、企業の業績も底上げされやすいのが特徴です。
新興国投資のリスク要因(政治リスク、カントリーリスク、為替リスク)
新興国には投資を行ううえで注意すべきリスクがいくつかあります。
- 政治リスク:政権交代や規制強化による影響
- カントリーリスク:財政赤字やデフォルトの危険性
- 為替リスク:通貨価値の下落による損失
特に、政府の方針が急に変わるような国では、企業活動に大きな打撃が出ることもあります。
これらを理解したうえで、国ごとの投資比率を調整することが大切です。
情報収集と分析の重要性
新興国投資では、常に最新の経済情報や政策の動きを把握しておくことが不可欠です。
たとえば、中国での規制強化、インドの金利政策、ベトナムの税制改革などは、株価に大きな影響を与えることがあります。
- 経済ニュースや政府の発表を定期チェック
- 信頼性のある専門家の意見を参考にする
- ファンド運用報告書で運用状況を確認



投資って数字だけ見ればいいと思ってましたけど、情報収集も大事なんですね!



そうなんです。情報が早いほど、判断ミスも減らせますよ。
為替変動の影響
新興国通貨は、円やドルに比べて変動が激しく、為替による損益が大きくなりがちです。
例えば、現地株価が上がっていても、通貨が急落すれば日本円ベースで損失になることもあります。
- 為替ヘッジなしのファンドは為替の影響を直接受ける
- 通貨安の時はリターンが目減りする
- 複数通貨に分散することで影響を緩和可能
為替の変動を見越して、投資のタイミングや比率を慎重に考える必要があります。
流動性リスク
新興国市場では、株式の売買がしづらくなる「流動性リスク」も注意が必要です。
市場規模が小さい国では、急な売買で価格が乱高下しやすく、希望するタイミングで売却できない場合もあります。
- 取引量が少ないと価格が安定しない
- 大口取引が価格に与える影響が大きい
- 市場が閉鎖されるリスクもゼロではない
そのため、投資先はある程度の流動性を持つ国やファンドを選ぶことも大切です。



新興国投資では「リスクを理解し、情報を味方につける」ことが成功の鍵です。
まとめ:新興国投資の組み合わせ戦略の有効性
オルカンと新興国投資を組み合わせる戦略は、分散効果と成長性の両方を手に入れる有効な方法です。
全世界に投資できるオルカンだけでも優秀ですが、新興国の成長をもっと取り込みたい場合には、別途ファンドを組み合わせることで、より高いリターンと安定性を両立できます。
- 新興国ファンドの追加でリターン向上を狙える
- 地域・通貨・セクターの分散が強化される
- 米国偏重のリスクを緩和できる
- 暴落時のダメージを複数資産で吸収可能
ただし、新興国投資には為替リスクや政治リスクなど、先進国にはない不確定要素も多いため、慎重なファンド選びと情報収集が欠かせません。
リスクを理解し、自分の投資目的と期間、リスク許容度に応じて比率を調整することで、長期的に安定した資産形成が可能になります。



先生、結局は「組み合わせ」が大事ってことですね!



その通りです。組み合わせ次第で、リスクを抑えながらリターンを狙える投資が実現できますよ。
これから新NISAで積立を始める方も、すでにオルカンを運用中の方も、ぜひ新興国投資とのバランスを見直してみてください。
少額からでも実践できるこの戦略は、あなたのポートフォリオに確かな「成長」と「安心」をもたらしてくれるはずです。



新興国ファンドをうまく取り入れることで、あなたの資産運用はもっと強く、もっと安定します。
今すぐ始められる、新興国投資との最適な組み合わせを見つけよう!
「オルカンだけで本当に大丈夫かな…?」と少しでも不安を感じた方は、今が見直しのチャンスです。
リスクを抑えつつ、新興国の高成長の波に乗るには、早めの準備と情報収集がカギになります。
まずは、少額から始められるおすすめの新興国ファンドを比較して、自分に合った投資スタイルを見つけましょう!
※NISA対応ファンドや、信託報酬の安い商品もチェックできます。
